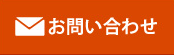このページでは不定期更新にて小牧山の自然の様子をお伝えします☆
【3月29日更新】
〇例年より早く桜が見ごろ
今年は春の訪れが早く、小牧山の桜が例年より早く開花。3月26日には八分咲きの桜を見に多数の方が訪れていました。
咲き乱れる桜の花へ蜜を吸いにメジロやヒヨドリが飛来。
冬鳥のシロハラがまだいました。
カエデの小さな花も咲き始めました。
タラの木の芽が伸び始めました。
大手道入り口脇の咲き始めたシャガ。
桜の次に小牧山を彩るツツジですが、もう数輪の花が咲いていました。
山頂に行くと市政60周年の2015年に誕生した小牧市のマスコットキャラクター「こまき山」が来ていました。こまき山と記念写真を撮る親子もいました。
大手道脇の土手にキランソウが咲いていました。
あと数日は歩きながらの花見が楽しめそうですね。
【3月10日更新】
○春の花々の準備が進んでいます
雨上がりの3月8日の午前中は曇り空。小牧山ふもとに植栽されているカタクリを見ると何本ものつぼみが出ていました。
近くにあるスイセンの花数が増えていました。
そこから四季桜に目をやると、こちらも花が増えています。
白梅のバックに赤いツバキを入れてみました。
梅園に行くと見ごろの白梅にメジロの群れが来ており、気ぜわしく花の蜜を吸っていました。
白梅近くで造園業者さんの桜の枝切り作業が始まると、メジロたちは咲き始めた紅梅へ移動。
雨上がりの花に着いた水滴を落とすのでしょうか。
梅園近くの紅白のアセビ。
ふもと東のハナモモのつぼみ。
1年ぶりにアカゲラと出会い撮影できました。曇り空のためシルエット状になった画像を補正しています。
朝早く梅園を訪れるとメジロの群れに出会うことができるかもしれませんよ。
【3月3日更新】
○風雨の中、紅梅にメジロの群れ
3月2日は強風を伴う雨が朝から降っていました。そんな中、傘を差しながら小牧山のふもとを歩いていると、東のふもとの花の盛りが過ぎかけた紅梅でメジロの群れが風雨に負けず吸蜜中。強い風に傘をあおられながらカメラが揺れないようにメジロを撮影しましたが、3分の1はピンボケ写真。
ふもとにあるあちこちの白梅の花数が増えてきました。
梅園の白梅も同様ですが、紅梅はあと少しで開花の感じに。雨の中、散策に訪れたグループも梅花を鑑賞。
梅園の梅の木に数羽のシジュウカラが飛来。
雨の中の観察でカメラも衣服も濡れましたが、まずまずの成果に満足。薄暗い場所で撮影したアオジやシロハラはピントが甘い写真ばかりでした。
【2月20日更新】
○雪とのコラボ
2月18日、小牧山に久しぶりの3センチの積雪。朝から雪が降り続くので、いつもより遅い10時から観察をスタートしました。南出入り口広場の雪の上をハクセキレイが歩いていました。
ふもと東の紅梅、合瀬川土手の白梅は見ごろを迎えていました。
雪降りのためウオーキングに訪れる人も少なめ。
オレンジ色のトキワサンザシの実と白い雪。
ピンクの紅梅と雪。
白梅と雪。
ふもとをいつも通り歩きました
梅園から西のトラツグミがいた草原を見ると、遊歩道で餌をついばむシジュウカラ。
シロハラやキジバトも出てきました。
雲の切れ間から薄日が差し始めたころにモズが。
このあと中日新聞の記者さんと出会い取材に協力。翌日の朝刊近郊版に、次のような記事が掲載。
【2月15日更新】
○トラツグミと3年ぶりの出会い
小牧山の自然観察を引き受けて1年が経過、その間に61回の原稿を作成しました。2年目を迎え新たな気持ちで小牧山観察を続け原稿を書かなければと思っています。観察には限りがあるため、同じような内容になる場合はお許し願います。
2月14日、小牧山に5日間来ないうちに南出入り口の河津桜が咲き始めていました。
ふもと東の紅梅、合瀬川土手の白梅は見ごろを迎えていました。
開花した花にメジロが訪れるのを待っていますが、まだ出会うチャンスに恵まれていません。
ふもと北の白梅はこれからのようす。
2週間前、1月29日には風花が舞う天気でしたが、立春を過ぎ小牧山は春の装いに少しずつ変化してきました。
ふもと北の梅園に行くと、シロハラが地面で餌探しをしていました。
梅園奥の草原を見ると、小牧山では3年ぶりの出会いとなるトラツグミが餌探しをしていました。トラツグミは夜中に笛のようなヒー、ヒョーと細い声で鳴くため、鵺(ぬえ)とも呼ばれ気味悪がられることもあります。しかし、バーダーには人気の鳥さん。
昆虫やミミズなども餌になりますが、この日は地面に落ちたクスノキの実を食べていました。
【1月27日更新】
○朝から食欲旺盛なヒヨドリ
1月26日の朝、南出入口にあるクロガネモチにヒヨドリの群れが集まっていました。ヒヨドリたちのお目当てはクロガネモチの赤い実。木の下の通路には食べ散らかした実が落ちていました。ヒヨドリの食欲には脱帽!
山頂の土手では地面で餌探しをするツグミがいました。
中腹の公園の薮のすき間からウグイスの姿が見えました。
ウグイスは「薮ウグイス」といわれ、あまり姿を見せてくれません。
羽根の色は「鶯色」の緑褐色で地味な色合い。
ウグイスと勘違いされるのがメジロ。
メジロは鮮やかな黄緑色をしています。
ふもとで一番よく出会うのがハクセキレイ。
ふもとの川沿い土手にある白梅が咲き始めていました。
友人から25日には花にメジロが来ていたとの情報も。
紅梅はこんな感じになっています。
まだ一部の梅しか咲いていませんが、これからの開花が待ち遠しいですね。
【1月23日更新】
○人なつこいヤマガラ
19日のお昼、中腹の公園に数多くのヤマガラが飛来。知人が手のひらにどんぐりをのせていると、ヤマガラがどんぐりをくわえようとやってきました。しかし、どんぐりが大きいのかあきらめて飛び去りました。
ヤマガラの群れと一緒にシジュウカラやメジロ、コゲラ、ジョウビタキも登場。
メジロやコゲラはちょこまかと動きまわるので、枝かぶりの写真になりました。
その日の朝、同じ公園で青いルリビタキと出会いました。今年は寒さが厳しいせいか、冬鳥と出会うチャンスに恵まれています。昨年、小牧山でルリビタキに一度も出会うことがありませんでした。
ふもとのアオジも人に慣れてきたせいか、近くをウォーキングの方が通過しても逃げないこともあります。
朝のふもとではツグミの声が目立っていました。
緊急事態宣言発令中。人との接触が少ない里山ですが、マスクを着用しお出かけを!ひょっとすると、珍しい冬鳥に出会うかもしれません。
【1月11日更新】
○冬鳥ルリビタキ
8日に小牧山北のつづら折りになった五段坂で今季初となるルリビタキと二度出会うことができました。翼に若干青みが出ているところからオスの若鳥と思います。成熟したオスは羽根全体が美しい青色になります。
ふもと東の紅梅が咲き始めていました。
2日間ともモズに出会いました。
10日、上空でカラスが騒ぐので見上げると、オオタカとカラスのバトル。写真が撮れたのはバトル後のオオタカが飛び去るところでした。
メジロも2日間とも登場。
羽繕いするようすも観察できました。
ふもとでよく出会うハクセキレイ。ゲットした木の実を飲み込むことができず苦労していました。
10日は前夜の雪が残っていました。
アオキ、アセビ、カラスウリの葉や実に雪が。
ふもと北のケヤキ並木では地面にも雪が。
れきしるこまき近くのエノキに1羽のイカルがいました。枝が邪魔をして上手く撮影できませんでしたので、3年前に撮影したイカルの写真をアップします。
年が明けてから寒い日が続いています。観察やウォーキングには、防寒対策を万全にしてお出かけを!
【1月5日更新】
○新年明けましておめでとうございます!
令和3年の新しい年が始まりました。友人からいただいた年賀状にコロナ禍の収束を願うコメントが数多くありました。御用始めの1月4日、新年早々の小牧山観察をスタート。冬休み中の親子、中学校や高校の運動部など数多くの来訪者でにぎわっていました。おめでたいことのシンボルとして松・竹・梅の3点が使われます。そのうちの一つの竹の節についての話題を。竹の節には輪がありますが、上の写真の輪は2つあり上の輪が角張っていないのでマダケ。ハチクの輪も2つですが、2つとも角張っています。太くて大きい竹のモウソウチクは節の輪が1つしかありません。
最初と最後にジョウビタキのメスを見ました。最初のジョウビタキはヘクソカズラの実を食べていました。
最後のジョウビタキは初め草むらの中に隠れていました。
その後、近くの枝にとまりました。
モズも合瀬川と休憩所の2か所に登場。
メジロは最初のジョウビタキの近くに登場。
ツグミは2番目のモズの近くのクロガネモチの実を食べていました。
お稲荷さんの近くのカナメモチとフユイチゴの赤い実が目立っていました。
観察を始めた時には青空でしたが約2時間の観察を終え帰るころ、雲が広がった市役所の上空に数羽のトビが飛来し旋回していました。
新年の観察スタートは代わり映えしないラインナップとなりました。
【12月28日更新】
○来年はよい年に!
あと4日で新しい年を迎える日となりました。あちこちで御用納めを迎え、明日からは年末年始の休みになる方も多いのではと思います。12月22日の小牧山観察で新年を迎えるのにふさわしいネタを探してみました。上の写真はマンリョウ、下の写真センリョウ。名前の由来はネットで調べれば出てくると思いますが、漢字で書くと「万両」と「千両」とお金に関するものが。
金額の大きさの差によりマンリョウは赤い実が下に、センリョウは実が上につきます。その他に「百両」「十両」「一両」と名づけられたものもあります。
年末近くになりましたが、まだ紅葉を楽しめる場所も。
紅葉をバックにしたモズ。
落ち葉の上でくつろぐキジバト。
ふもと北の低木にアオジがいました。
近くのツツジの仲間には季節外れの花が数輪。
合瀬川にはダイサギとコサギ。
木の葉を落とした枝にスズメバチの巣を見つけました。
今年は年明け早々からコロナ禍となり、かつて経験したことのない大変な年となりました。来年はコロナ禍が収まることを願いたいと思っています。年明けは年末年始の休み中の観察が報告できるのではと思います。みなさま、よいお年をお迎えください。
【12月21日更新】
○冬鳥のツグミを見るようになりました。
12月18日、小牧山ふもとのれきしるこまきや休憩所近くでツグミの群れを見ました。
エノキやクスノキに飛来し、その実を食べるようすが観察できました。
同じ日、ふもと北のケヤキ並木ではヤマガラやシジュウカラ。
ヤマガラは口に入らないようなどんぐりをくわえていました。
ふもと東の広場で日向ぼっこをするジョウビタキのメス。
15日、咲き始めた桜の馬場のヤブツバキでヒヨドリが蜜を吸う姿。
日陰のカエデが色づき、まだ紅葉を楽しむことができます。
ヤブツバキと紅葉のコラボも。
初雪が降り暖冬から一気に真冬の寒さとなりました。防寒対策を万全にしお出かけを。
【12月14日更新】
○ モミジバフウにカワラヒワ
写真の整理がなかなかできず11月28日から12月7日までの観察をまとめました。12月1日と7日の観察では、ふもと北のモミジバフウにカワラヒワの群れが飛来し、実をついばむ姿が観察できました。上の写真はカワラヒワとメジロとのコラボ。
上が1日、下が7日の観察写真。モミジバフウの木を見上げると、カワラヒワを見ることができるかもしれませんよ。
11月下旬から小牧山に飛来するトビが目立つようになりました。多いときには6羽のトビが上空を旋回していました。
下は12月4日、脚に何かを持ちながら飛んでいました。
飛来するトビに対し小牧山をねぐらにしているカラスたちが攻撃をしかけるようすを何度もみました。
上は11月28日、下は12月1日。
他の小鳥も撮影しましたが、枚数が多くなったのでここまでにします。
【12月1日更新】
○上空でオオタカとカラスの空中戦
11月24日、山頂に着き上空を眺めていると、オオタカとカラスとが空中戦。
動きが速いのでピントが甘めなのはお許しを。
ふもとの四季桜近くのムラサキシキブではジョウビタキのメスがお食事。
オスはクスノキの中で実を選んでいました。
四季桜の花見も。
すぐ近くでメジロやシジュウカラ。
モズも。
紅葉&黄葉を終えた葉は散り始め枝だけの姿に変わりつつあります。
【11月16日更新】
○今の季節は春夏秋冬?!
11月10日の小牧山の自然観察。これから紹介する写真から今の季節はいつだと感じるでしょうか。北東の出入り口近くにある四季桜。
ふもとを西に少し歩いた木の枝には夏鳥のコサメビタキ。
山頂に向かう中腹の周回路で花数を増した白とピンクのサザンカを観察。
北の中央にある出入り口付近の紅葉・黄葉は
林床の低木周辺を動きまわる冬鳥のアオジ。
冬に咲くツワブキやサザンカの花。
これらの写真から今の季節はいつだと思いますか。
【11月9日更新】
○山頂の上空に2羽のオオタカ
11月4日は朝からよい天気。小牧山の山頂で観察していると、上空に2羽の小型のタカが飛来。写真で確かめるとオオタカ、体の白い個体が成鳥で茶色いのが幼鳥と思われます。
少し前の10月29日の山頂ではヒサカキの実を食べるカワラヒワの群れを見ました。冬になるとカワラヒワと出会うチャンスが多くなります。
山頂に向かう中腹の周回路で花数を増した白とピンクのサザンカを観察。
チャの木の花や実も。
ふもとのハギの花にはウラナミシジミ。
別の場所では日光浴をしているムラサキシジミ。
ムラサキシキブの実とジョウビタキのメスとのコラボ。
四季桜の花とジョウビタキのオスとのコラボ。
普段あまり歩かない梅園奥でケヤマウコギの実を見つけました。
その近くにはよく似た感じの実のカクレミノが。
小牧山ではありませんが、数日前に冬の渡り鳥のツグミを市内東部で見ました。どんな冬鳥と出会えるか楽しみな季節になってきました。
【10月27日更新】
○冬鳥と夏鳥との両方を楽しむ
10月20日は朝から好天の小牧山で観察。東のふもとで冬鳥のジョウビタキのオスとは、今季初の出会い。
休憩所近くのしだれ桜で動きまわるセンダイムシクイ。冬鳥のジョウビタキが訪れましたが、夏鳥のセンダイムシクイは名残を惜しんでいるよう。
その近くには夏鳥のサメビタキもいました。
渡りの途中と思われるタカの仲間のノスリが山頂に向かって飛んでいきました。
この日は数多くの小鳥とあちこちで出会うことができました。ノブドウの実を食べに来たメジロ。
シジュウカラやヤマガラ。
好天のため遠くの雪山もきれいに見えました。
この観察から1週間後の27日、まだ夏鳥と出会いました。その報告は次の原稿で。
【10月16日更新】
○ 少しずつ秋の色合いに
コロナ感染症が世界中に広がり始めた2月からスタートした小牧山の自然観察は今回で50回目になりました。依頼されたとき自分のブログもあるので継続できるか不安でした。ところが始めてみると小牧山で自然観察する機会が増えたことにより、今まで以上に出会う野鳥や木々の花なども増えました。今回は好天だった10月13日と15日の観察をまとめました。上の写真は桜の馬場で、下の写真は五段坂で見つけたカラスウリ。9月から探していてやっと出会うことができました。カラスウリは秋の童謡「真っ赤な秋」の歌詞にも出てきますね。
ふもとの樹上にあるノブドウの実も色づいています。
周辺によい香りが漂わせるキンモクセイが咲き始めました。次の写真はお稲荷さん近くの大手道、その下の写真は北のふもとの木立の中。山頂の遊歩道脇にもありますが、遊歩道の整備工事のため通行ができない場所。
遊歩道がかなり傷んできたため、大がかりな補修が行われる予定。
ふもとのケヤキは葉を落とし始めました。
オオルリの幼鳥との再会を期待しふもとを歩いていると、カエデの中から「チ・チ・チ」という小さな鳴き声。声の主を必死で探してみると、瑠璃色のオオルリではなく黄色いキビタキのオスが。
幸運なことに近くにキビタキのメスもいました。
上は13日、下は15日と2回連続での出会い。
15日にはセンダイムシクイとも。
萩の葉っぱにウラナミシジミ、幼虫の食草はマメ科植物。
木々が葉を色づかせたり落としたりし小牧山は少しずつ秋の色合いになってきました。
【10月12日更新】
○夏鳥との別れの季節に
暑いと思いつつ過ごしていた9月が終わり、10月になると朝晩が涼しくなりました。それに合わせるかのように、春の飛来から今まで姿を見せなかった夏鳥が南に渡る途中で小牧山を訪れました。10月2日は山頂でオオルリのメス(3番目の写真)、4日はふもとでキビタキのメス(4番目の写真)、9日はふもとでオオルリのオスの幼鳥(最初と2番目の写真)に出会いました。
コサメビタキはすべての日に出会いました。
遊歩道に小さなクリの実が落ちていました。
ふもとのアラカシはたくさんのどんぐりが実っています。
花が終わったクサギに青い実が。
イタドリの実が目立ってきました。
イタドリは雌雄異株で実がつくのはメス株。
オス株はこんな感じ。
クチナシの葉でオオスカシバの幼虫を見つけました。
中腹の桜の馬場で見つかったスズメバチの巣は写真を撮った翌日に駆除されました。
秋はスズメバチの活動が活発になる時期、巣を見つけたら近づかないようにしましょう。
【9月30日更新】
○3日連続でセンダイムシクイ
前回報告した夏鳥のセンダイムシクイと翌日から2日間出会うことができました。
25日は雨の中の観察でしたが、いつもの中腹公園に飛来。
前日は大手道を歩いていると目の前をセンダイムシクイ通過し薮の中に。動かずじっとしていると、薮の中から足下1mほどのところに登場。ロケーションは今一つですが撮影しました。
雨の中、山頂でも咲き始めた四季桜に気づきました。雨で薄暗かったので花が目立ったかもしれません。
青年の家前の坂道に咲くヒガンバナにクロアゲハが飛来。
同じ場所で数年前にはモンキアゲハやナガサキアゲハのメスと出会いました。クロアゲハのオスは後翅の前縁に薄黄色のラインがあります。
中腹の公園でミドリヒョウモンが飛来、今年は出会うチャンスが多いようです。
公園の高い木のてっぺん近くにコサメビタキ。
メジロの群れも訪れ、運よく2羽の姿を撮影できました。
雨の日の山頂でもメジロの群れ。
公園の片隅に白いヒガンバナ。
朝晩めっきり秋らしくなってきました。
コロナ禍の中、体調管理に気をつけ生活したいと思います。
【9月25日更新】
○夏鳥との別れの季節
台風12号がコースを右にとり、少し前の天気予報では雨だったのが思わぬ好天になった9月24日は、久しぶりにふもとから中腹までをじっくり観察しました。中腹の桜の馬場で夏鳥のコサメビタキが何度も飛来し楽しませてくれました。小牧山では夏鳥が渡ってくる4月末と渡っていく9月末に出会うチャンスがあります。
今年、市民四季の森では9月初旬からコサメビタキを観察しており、小牧山への来訪を心待ちしていました。
コサメビタキを観察していると、近くの薮の中で動きまわるウグイスに似た小鳥。カメラを通して見ると夏鳥のセンダイムシクイ。
コサメビタキより出会うチャンスが少ないですが、小牧山では4月下旬と9月~10月下旬に観察したことがあります。
市民四季の森では今年8月下旬に出会いました。
夏鳥が渡り終えるのと入れ替わりに冬鳥が訪れます。
ふもとにある四季桜が咲き始め、蜜を吸いにメジロが来ていました。
ふもとの所々のソメイヨシノにも花が観察できました。
前回に紹介したミドリヒョウモンがクスノキの幹に産卵していました。ヒョウモンチョウの仲間の食草はスミレ類なので、スミレに産卵するものと思っていましたが、ミドリヒョウモンはスミレが近くにある樹幹に産卵するとのこと。
ノブドウで蜜を吸う数頭のアオスジアゲハ。
ふもと東の土手のヒガンバナは間もなく見ごろの感じ。
秋の色合いをバックに鳴くツクツクボウシ。
真夏に比べ汗ばむことが少なくなりました。
初秋の小牧山を訪れてみませんか。
【9月25日更新】
○ 秋の気配を感じるように
前回から少し時間が空きましたが、9月15日と18日の観察。
大手道中腹の草原にススキの株を見つけました。
秋の七草のフジバカマと同じ仲間のヒヨドリバナも咲いています。
ふもと東のトキワサンザシの実が赤く色づき始めています。
北のふもとにあるセンニンソウ、早く咲いた花は種ができはじめています。
その花にいつも見ているツマグロヒョウモンとは違うヒョウモンチョウが飛来。
図鑑で調べてみると、ミドリヒョウモンのようです。
ヒョウモンチョウの名前の由来は、黄色の地に黒い斑点が並んだヒョウ柄模様から。
幼虫の食草はスミレ類、身近にいるツマグロヒョウモンはパンジーを食べています。
前回に続きトチノキの実を拾いました。
大手道にはタラノキの花も咲いています。
小鳥と出会うチャンスが増え、メジロ、ヤマガラ、シジュウカラを観察。
夏の終わりを告げるかのようにツクツクボウシが鳴いています。
【9月18日更新】
○ スズメバチの狩り
前回はシジュウカラの青虫ゲットでしたが、9月8日はスズメバチの狩りに出会いました。ガガイモの花を撮ろうとカメラを向けると、そこにアオスジアゲハを獲物にしたスズメバチがいました。スズメバチがとまっていたのはガガイモの実。ガガイモの実については継続観察したいと思います。
北のふもとにあるトチノキの下に行くと熟した実が落ちていました。前日の台風10号の強風も落下に影響したと思います。
大小とりあわせて10個以上の実を拾ってきました。この実は観察会の資料として保存する予定でいます。
ノブドウの花で蜜を吸うアオスジアゲハ。
れきしるこまき近くのクサギではアゲハチョウが吸蜜。
お昼ころもう一度行くと、今度はクロアゲハが蜜を吸っていました。
ウスバキトンボの休憩に二度出会うチャンスがありました。
飛んでいる姿にもチャレンジ。
真夏に比べ涼しくなりましたが、観察を終えるころには汗をかきました。
【9月7日更新】
○ 小鳥の姿が目立つように
9月1日と4日の朝、1時間ほど大手道から山頂までを歩きました。山頂で獲物の青
虫をゲットし飛び立ったシジュウカラを運よく撮影できました。
上はその直前の写真、右下の葉に獲物の青虫がいます。
写真は中腹で撮影。
近くにはヤマガラやコゲラもいました。
大手道沿いの草むらで休むナガサキアゲハのオス。ナガサキアゲハはクロアゲハより一回り大きく後翅の尾状突起がありません。
前日降った雨水を地面から吸うヒメアカタテハ。
コチャバネセセリは鳥の糞から栄養補給も。
山頂近くの草原にはバッタの仲間、これはオンブバッタでしょうか。
次のバッタの仲間はツチイナゴの幼虫。
ハムシの仲間、クロウリハムシ。
まだ暑い日が続いており、1時間ほどの観察を終えると汗びっしょりになります。
【8月28日更新】
○ミンミンゼミの鳴き声を聞きました
8月25日、用事で中腹にある青年の家に立ち寄ると近くからミンミンゼミの鳴き声が聞こえました。写真を撮りたいと姿を探しましたが見つけることができませんでした。10日ほど前、青年の家に「小牧山にミンミンゼミはいませんか」と尋ねる母子が来訪。偶然いた私に事務局の方から声がかかり、小牧市内で一年に一度出会えるかどうかの珍しいセミだと話をしました。ちょうどそんなころ中日新聞近郊版の支局記者さんのセミを話題にしたコラムが掲載。関東出身の記者さんにとって身近なセミはミンミンゼミだったのが、愛知県西部に来てその鳴き声を聞かないとのコメントが。上の写真は一年前の小牧山大手道近くで撮影したミンミンゼミ。
この写真は平成28年に小牧山で撮影。
この写真は平成29年にふれあいの森で観察したミンミンゼミ。
平成26年に兒の森(ちごのもり)で観察したミンミンゼミ。
8月22日と25日に観察したものを紹介します。
大手道沿いの石灯籠でツクツクボウシの抜け殻を見つけました。
中腹で撮影したツクツクボウシ。
東遊歩道のヤブミョウガにとまったコノシメトンボ。
北のふもとにあるセンニンソウで吸蜜するアゲハチョウ。
青年の家2階の窓から観察したシジュウカラ。
一緒にいたメジロ。
子育てが一段落してきたので、小鳥たちと出会うチャンスが増えました。
【8月17日更新】
○ ガガイモにホシホウジャク
前回のアップから少し時間が空きましたが、自然観察は継続しています。
みなさんのお盆休みの8月12日はふもとだけ、15日は山頂まで歩きました。
タイトルのガガイモ?と思われた方が多いのでは。
ガガイモは荒れ地や道ばた、川の土手などに普通に生える野草。
アサギマダラの幼虫はガガイモの仲間のキジョランやイケマなどを食べて育ちます。
ガガイモの仲間はアルカロイド毒を含んでおり、アサギマダラの体内にはその毒が残
ることで野鳥など敵から身を守っています。
クサギの花でもホバリングしながら蜜を吸うホシホウジャクがいました。
ホシホウジャクはオオスカシバと同じガの仲間。
飛んでいる姿はハチのように見えます。
幼虫はヘクソカズラの葉を食べます。
ホシホウジャクやオオスカシバのホバリングしながら蜜を吸う姿からハチドリを連想。
クサギにはチャバネセセリも吸蜜。
ガのように見えますが、チャバネセセリはチョウの仲間。
ふもとを群れて飛ぶトンボが運よく木の枝にとまってくれました。
このトンボはウスバキトンボで、全世界の熱帯や亜熱帯で生息。
初夏のころ南国から飛来し、北に向かって分布を広げるが4℃以下では死滅します。
12日、山ぎわの遊歩道脇にあるエノキでゴマダラチョウの幼虫を見つけました。
15日にもう一度観察しようと行きましたが、幼虫を見ることができませんでした。
ところが少し離れたエノキで幼虫と出会うことができました。
北のふもとの生け垣を覆うように咲くセンニンソウ。
白い4枚の花びらに見えるのはがく片。
キンポウゲの仲間で有毒のため、牛や馬は食べないとのこと。
山頂より少し低いところにあるシイノキの樹液を吸うルリタテハがいました。
かなり前から鳴き始めたツクツクボウシがやっと撮影できました。
山頂では数頭のナナフシも観察できました。
小牧山の横を流れる合瀬川を泳ぐナマズを見つけました。
連日、暑い日が続いています。
木陰は日向に比べ若干涼しいと思います。
熱中症対策やヤブ蚊対策をし、小牧山を散策してみませんか。
【8月2日更新】
○周辺に芳香が漂っています
東海地方もようやく梅雨明け。
7月29日と31日に汗をかきながら小牧山のふもとを歩きました。
小牧山ふもと東の合瀬川にかかる御幸橋(みゆきばし)周辺に盛りを迎えたクサギの花が咲いています。
クサギの名前は葉の臭気からつけられました。
においの感じ方は個人差があり、観察会で参加者に尋ねるとにおいが嫌な人とそうで
ない人とは半々。
私はピーナッツバターのように感じ嫌ではありません。
その花の蜜を求めいろいろな昆虫が訪れています。
オオスカシバという蛾の仲間も。
つぼみに飛来したツマグロヒョウモンのオス。
私の知人は同じ場所を通ったときスマホでナガサキアゲハのメスを撮影しました。
それを期待して二度出かけましたが、今のところ私の願いは叶えられません。
アゲハチョウも飛来しましたが、蜜を吸わずに通過していきました。
何頭ものクマバチも来ています。
近くにハグロトンボがいました。
前回と同じ青年の家近くの桜にニイニイゼミがいました。
クマゼミは一番よく出会います。
市役所に近いふもと南に群れで飛ぶトンボ。
とまってくれないので飛んでいる姿を撮影しました。
毎年、ふもと東を群れて飛んでいるウスバキトンボかと思います。
ふもと南の植え込みでしぼみかけたカラスウリの花がありました。
夜ならばもっときれいかと思います。
【7月27日更新】
○3種のセミを見つけました
曇天の7月21日と24日に小牧山を歩きました。
最初に見つけたのは小さなニイニイゼミで、青年の家近くのカエデの幹にいました。
私が子どものころ身近にいたセミですが、生息環境が変化し数が減っています。
小牧山にまだいるということは、小牧山の自然が保たれている証だと思います。
なき声が一番よく聞こえるクマゼミはあちこちで見ることができました。
ニイニイゼミと反対に私が子どものころ数が少なく貴重種だったクマゼミが増えてき
ました。
南方系のセミですが、温暖化の影響や生息環境のあう場所が増え関東地方まで分布を
広げています。
アブラゼミはこれから数が増え、観察する機会が増えると思います。
私が子どものころ一番多くいましたが、最近はクマゼミの方が多くなりました。
ところどころでセミの抜け殻がありました。
泥まみれの小さな抜け殻はニイニイゼミ。
クマゼミとアブラゼミの抜け殻は勉強不足で区別できません。
カミキリ虫の仲間のヨツスジトラカミキリ。
アシナガバチに擬態しているとのこと。
カミキリ虫は種類が多く、名前のよく似たヨツスジハナカミキリもいます。
台湾から東南アジア原産の帰化昆虫のキマダラカメムシ。
サクラ、カキ、サルスベリ、ナンキンハゼなどにつき、公園や神社、街路樹で観察できます。
小さなシジミチョウの仲間のヤマトシジミ。
キチョウもいました。
タブノキの葉にアオスジアゲハの幼虫。
アオスジアゲハの幼虫はタブノキやクスノキの葉っぱを食べて育ちます。
前夜に咲き終わったカラスウリ、夕方か夜ならば花を見ることができます。
【7月20日更新】
○花の種類が増えています
雨が降る7月14日と曇り空の17日に小牧山を歩きました。
ムクゲの花数が少しずつ増えてきました。
1輪1輪は一日で咲き終わりますが、次々と花を咲かせます。
花が終盤を迎えたアパガンサスには実ができはじめました。
川沿いの土手にあるクサギにつぼみ。
名前の由来は臭い木からですが、感じ方には個人差があるように思います。
アゲハの仲間が蜜を吸いに来るのが待ち遠しいですね。
白い花が目立つタカサゴユリにもつぼみが。
咲き始めたムラサキシキブの花。
秋になると紫色の小さな実がなります。
早く咲いたヤブミョウガには実ができはじめました。
白い実はしだいに藍色に変わっていきます。
雨にぴったりのカタツムリ、14日には3匹と出会いました。
萩の葉に小さなゾウムシの仲間がいました。
17日、あちこちからクマゼミの鳴き声を聞きましたが、姿を見ることができません
でした。写真を撮ることができしだいアップしたいと思います。
【7月13日更新】
○雨にも負けず活動
雨が降る7月6日と10日に小牧山を歩き、前半は10日の観察記録をまとめました。
南出入口の土手に広がって生えるヤブガラシの花に数多くのアオスジアゲハが訪れていました。
雨の中、数羽のドバトが休憩。
ふもと東の土手にあるサルスベリも花数が増えてきました。
いろいろな生きものによく出会うふもと北のアジサイにコウガイビルが。
ふもと北ではハグロトンボも。
後半は6日の観察。
アミガサハゴロモの成虫と幼虫(上の方の白いもの)。
カメムシの仲間ですが、カメムシのように臭い匂いを出しません。
下は10日に撮影したアミガサハゴロモの成虫。
キマダラセセリが休憩。
ハクセキレイの幼鳥。
ヤブガラシにはスズメバチも来訪。
雨の日の小牧山ふもとで、いろいろな生きものたちと出会うことができました。
【7月3日更新】
○晴れの日と雨の日
今回も晴れた6月26日と29日、雨の30日に小牧山を歩きました。
晴れた日はカメラ目線でサービスのカマキリ。
雨の日はサービスなし。
晴れた日のアジサイにハチの仲間が訪れていました。
ヤブミョウガにも花が目立つ場所も。
ふもとも山頂もヘクソカズラが咲き始めました。
れきしるこまきの土手のサルスベリも。
ムクゲは花数を増やしました。
青年の家の玄関にナナフシ。
山の中の暗い場所にもナナフシ。
晴れた日と雨の日は…。
【6月26日更新】
○新しい花が咲き始め
雨の6月19日、晴れた22日と23日に小牧山を歩きました。
北の入り口近くのギボウシが咲き始めました。
市役所近くの道路沿いでは白いムクゲも。
桜の馬場周辺のヤブミョウガにも花が。
ミョウガという名前ですが、食べるミョウガとは別種なので注意を。
草むらの中にあるセンリョウにはつぼみ。
エゴノキの実を観察していると、形の違うものがありました。
これは「エゴノネコアシ」と呼ばれる虫こぶ、アブラムシが原因とか。
コブシには「にぎりこぶし」のような実。
薄暗いところにあるアジサイの葉にハグロトンボがいました。
アジサイのがく片に卵、蛾の仲間のものでしょうか。
雨の日に外周コースを歩いて2匹のカタツムリを見つけました。
雨の日と晴れた日の松ぼっくり。
湿度が高いと鱗片を閉じ、乾燥すると鱗片を開きます。
前回、紹介した脚が再生中のナナフシ。
同じ個体ではありませんが、短い脚が再生したナナフシを見つけました。
【6月19日更新】
色づき始めたヤマモモ
6月16日、桜の馬場脇にあるヤマモモを見上げると実が色づき始めていました。
その周辺を観察していると、昼間に活動するホタルガやカノコガ。
赤い頭部に櫛状の触覚、翅は黒地に白い帯のホタルガ。
翅の鹿の子模様から名づけられたカノコガ。
ハチのように見えるのも蛾の仲間のコスカシバ。
ドロバチに擬態しているとのこと。
蛾の仲間のように見えるのは蝶のキマダラセセリ。
チャバネセセリも蝶の仲間
山頂近くの暗い場所でセアカツノカメムシのカップル。
緑と赤が目立つカメムシですね。
アジサイにカマキリの幼虫。
遊歩道でキマワリ。
子どものころの虫取りでクワガタかと思いがっかりした記憶が。
数多く観察したナナフシの中に再生中の脚のものが。
先端が丸まった右前脚、次の脱皮で元通りの脚になります。
【6月15日更新】
○梅雨にぴったりカタツムリ
6月12日、梅雨入りした東海地方では雨と曇りを繰り返す天気。
そこで桜の馬場周辺で梅雨時にぴったりあうカタツムリを探しカエデの幹で見つけました。
ふもとの道路沿いにある花壇で咲き始めたアパガンサス。
大手道から上ったお稲荷さんのアジサイが見ごろに。
花をアップにすると。
れきしるこまき近くのクズの葉にはバッタやカマキリの幼虫、小さいコガネムシの仲
間がいました。
青年の家近くのクチナシは花数を増し周辺によい香りが漂っています。
薄暗いところで咲くサカキですが、桜の馬場近くでは明るい場所で観察できます。
ふもとから桜の馬場まで歩いた観察でも、これだけ楽しむことができました。
【6月12日更新】
○クチナシやサカキ、ナンテンなどが開花
6月9日、天気予報では梅雨入り前日、青年の家やれきしるこまきの近くにあるクチナシが咲き始めました。写真のように一重と八重の2種類があります。
山頂手前の薄暗い遊歩道でサカキの花も咲き始めていました。漢字で「榊」と書き神事の玉串に用いられます。
ふもとから中腹にかけてあるナンテンも。一般に南天で知られており、その読みが「難
転」に通じることから縁起のよい木として好まれています。
れきしるこまき近くのナツツバキは花数を増やしてきました。
大きな木になるので気づかないかもしれませんが、アカメガシワの雄花も咲き始めて
います。この木は雌雄異株で、しばらくすると雌花も咲き始めると思います。
五段坂のコジキイチゴの実が色づいてきました。
花の終わったエゴノキに実ができてきました。
タブノキの実が大きくなってきました。
咲きそろってきたアジサイの萼片に小さなバッタの仲間。調べてみるとクダマキモド
キの幼虫のようです。
青年の家近くのエノキにかなり大きくなったナナフシを見つけました。
東海地方も梅雨入りとのこと、雨間の時間のウオーキングで自然を楽しんでみません
か。
【6月6日更新】
○アジサイが咲き始めました
6月5日、東海地方はまだ梅雨に入っていませんが、梅雨時に似合う花「アジサイ」が咲き始めました。
アジサイの白い花びらに見えるのは「萼片(がくへん)」で中央に小さな花が集まっています。
見ごろを迎えた山頂近くのネズミモチにチョウの飛来を期待しましたが、飛び回っていたのはクマバチとタイワンタケクマバチばかりでした。
麓のアジサイの近くで4つの花をつけるヒルガオ。
トチノキの実が大きくなってきましたが、半分以上は落ちてしまっています。
トキワサンザシの実はたくさんの実をつけています。
リョウブのつぼみが大きくなってきました。
この花にチョウが飛来するのを待っています。
桜の馬場近くの階段で不気味なオオミスジコウガイビルを見ました。
ヒルという名がついていますが血を吸うことはなく、ヒルとは違うプラナリアに近い
仲間。普段はミミズなどと同じように落ち葉の中におり、ナメクジなどを食べているようです。オオミスジコウガイビルは外来種で1mくらいになるものもいます。
【6月2日更新】
○少し大きいシジミチョウ
5月29日、小牧山の数か所で飛ぶ少し大きめのシジミチョウを見ました。
翅の裏側が真っ白なチョウで、ウラギンシジミ。
表側の朱色が見えるのがオス、メスは水色と色が違います。
咲き始めたネズミモチに来たアオスジアゲハ。
梅園の遊歩道では地面の水を吸うことも。
咲き始めたクロガネモチの花にスズメバチ。
昨年の実が残っていても、花をつけるクロガネモチ。
何か所かでシオカラトンボのメス。
シオカラトンボのメスはムギワラトンボという名前もあります。
ふもとで目立つ白い穂はチガヤでしょうか。
非常事態宣言は解除されましたが、コロナウイルスに対する注意を怠ることはできません。小牧山を散策するときにも注意を!
【6月1日更新】
ナナフシ特集
これから小牧山でみることができる不思議な昆虫「ナナフシ」をご紹介します!
ナナフシ(ナナフシモドキ)
九州大学名誉教授で昆虫学者の安松京三氏は農学博士の学位論文をナナフシの成長解析の研究で取得されました。昭和17年発行の宝塚昆虫館報に竹節虫の卵という論文でナナフシの仲間の卵を紹介しています。竹節虫という名は竹の節のような虫ということで、七節(ななふし)は節がたくさんあることから名付けられました。
木の枝に擬態していると言われる不思議な昆虫のナナフシを紹介したいと思います。
小牧山ではソメイヨシノの花が散り、若葉が少し大きくなったころに卵からふ化をします。その後、脱皮を繰り返し6月下旬頃に成虫になり、10月ころまで生きているものもいます。広葉樹の葉を食べますが、小牧山ではサクラの葉によくいます。採取したとき口から緑色の液を出しますが毒ではありません。
ナナフシの不思議①
ごくまれにオスがいますが、小牧山で見るのはメスばかり。それでは卵がふ化しないのではと思いますが、単為生殖という方法でメスが産んだ卵はふ化し成長します。
ナナフシの不思議②
ナナフシの脚は敵に襲われた場合に簡単に取れてしまいます。取れた脚は成虫になるまでの脱皮で再生します。
ナナフシの不思議③
ナナフシを見つけ採ろうとすると、そのまま地面に落下し硬直したようになります。敵を欺くため死んだふりをしています。
ナナフシの不思議④
ふ化したばかりの時は緑色をしていますが、成虫になるにしたがって茶色の個体も出てきます。明るい場所で成長した個体は緑、暗い場所の個体は茶色が多いと思います。
ナナフシの不思議⑤
飼育して卵を観察すると、植物の種子のような形をしています。
ぜひ小牧山で不思議な昆虫「ナナフシ」を探してみてください!
【5月27日更新】
〇小白いブラシのような花
5月23日にはつぼみばかりだったズイナが、26日には白いブラシのような花をつけていました。
ふもと東のエゴノキでタイワンタケクマバチとクマバチが蜜を吸っていました。
タイワンタケクマバチはその名の通り、中国から輸入された竹材と一緒に入ってきた外来種。
タイワンタケクマバチは体全体が真っ黒ですが、クマバチは胸が黄色でキムネクマバチとも呼ばれています。
スイカズラの花でチャバネセセリが蜜を吸っていました。
セセリチョウの仲間は蛾のように見えますが、蝶の仲間。
花が終わったエゴノキに実ができはじめていました。
梅園の梅の木の下にいくつかの実が落ちていました。
大きな松の木の下には松葉と一緒にご覧のようなものがいっぱい落ちていました。
これは松の雄花で雌花は松ぼっくりになります。
咲き始めたハゼノキの花にはミツバチが訪れていました。
山のあちこちにあるクロガネモチも咲き始めました。
野草のドクダミも花数を増やしてきました。
ドクダミは強い臭気がありますが、古くから民間薬として利用しています。また、天ぷらにして食べたり、乾燥させた葉をドクダミ茶として利用をしています。
生薬名は「十薬(じゅうやく)」。
【5月22日更新】
○スズメも獲物をゲット!
5月18日と20日、身近な鳥のスズメが目立ちました。
ふもと北では青虫や甲虫をくわえるスズメを観察。
中腹の大手道の両側に盛りを迎えたテイカカズラ。
名前の由来については諸説あるようですが、歌人の藤原定家に由来するものも。
つる植物なので枯れた木を包み込んでいました。
青空をブックにした白いエゴノキの花がきれいでした。
エノキの周囲を飛ぶゴマダラチョウが一休みしたところを撮りました。
幼虫の食草がエノキ、秋の終わりに根元の枯れ葉で越冬した幼虫が若葉が出てから木に登りさなぎとなり羽化します。
ウツギの花にクマバチ。
ふもとのヤマボウシの花が咲き始めました。
五段坂のマユミの花、ふもとのマユミも咲いています。
梅園近くの地面で動き回るスズメバチがいました。
脱皮し一回り大きくなったナナフシ。
非常事態宣言が解除され、小牧山を訪れる人が少しずつ増えてきました。
【5月15日更新】
○獲物をゲット!
5月13日、中腹の桜の馬場に来ると、薮の中から飛び立った小鳥が。
カメラで姿を確かめると黒・白・黄が印象的なキビタキ。
そのクチバシにはゲットしたばかりの青虫。
食べ終わったあと、何もなかったようなポーズをしてから飛び去りました。
花数を増やしてきたトキワサンザシには数多くのアオスジアゲハが蜜を吸いに来ていました。
五段坂途中のコジキイチゴにもアオスジアゲハが。
咲き終わった花には実ができはじめていました。
咲き始めた小さなマユミの花。
ふもとでは白い特徴的なエゴノキの花が咲き始めました。
その花にハナムグリが来ていました。
梅園近くの地面で動きまわるスズメバチがいました。
最近咲いているのは白くて小さい地味な花が多いですが、足を止め観察してみると新たな発見があるかもしれません。
【5月13日更新】
○センダンの花
5月11日、市役所交差点近くの喫茶店横の空き地にあるセンダン。
淡い紫色をした数多くの小さな花をつけ始めました。
お稲荷さん近くのカナメモチの周辺をアオスジアゲハが飛び回って蜜を吸っていました。
前回の感圧よりも花数を増やしたスイカズラにはクマバチ。
前日の雨が上がりご覧のような青空。
山頂からの眺めも楽しめました。
山頂のハルジオンにもアオスジアゲハ。
前回、「五段坂の途中でエビガライチゴ」と紹介しましたが、「コジキイチゴ」の誤りでした。訂正しお詫び申し上げます。
【5月8日更新】
○春の花が続いています
5月8日、市役所前の道路沿いのシャリンバイが咲き始めました。
ふもと東にはピラカンサスと呼ばれるトキワサンザシの花も。
東から山頂方向を見上げると、写真のような花が見えます。
これはシイの木の花。
北東のふもとのハリエンジュが咲き始めました。
ハリエンジュは豆の仲間なので、一つひとつの花が豆の花と同じ形をしています。
ベンチで日向ぼっこをするシオカラトンボのメス。
このトンボは一般にムギワラトンボと呼ばれています。
北のふもとで脱皮直後のナナフシを見つけました。
葉っぱについた部分はナナフシの抜け殻。
五段坂の途中でエビガライチゴや小さなスミレの花。
山頂で咲き始めたスイカズラを見つけました。
スイカズラのようにつる性植物には○○カズラという名前がよくついています。
桜の馬場の遊歩道沿いにある高木のセンダンにも花。
ツツジにクロアゲハが来ていました。
GW中に比べ訪れる人の数が少なくなりました。
【5月4日更新】
○アゲハチョウとキアゲハ
ゴールデンウィークの5月1日と3日、小牧山を歩きました。
咲き乱れる春の花々にアゲハチョウやキアゲハが訪れていました。
この2つのチョウはとてもよく似ています。
見分け方は前の翅の体に近い部分が黒いかどうか。
アゲハチョウは黒い筋になっていますが、キアゲハは黒くなった部分があります。
上の写真がアゲハチョウ、下がキアゲハ。
トチノキの花が見ごろになり、遠くからでも目立っています。
桜の馬場のツツジも見ごろになり、スマホで撮影する人の姿も。
小牧山ならば三密を避けることができるのではと、ウオーキングやランニング等で訪れる人も増えています。
【5月1日更新】
○チョウが活発に活動
4月29日、小牧山ふもと東の広場にあるウツギにアゲハやアオスジアゲハがきていました。
ふもと北の梅園ではツマグロヒョウモンのオスがいました。
オオルリやキビタキを観察した桜の馬場のユリノキの花が咲き始めました。
ふもとにあるユズリハは地味な花をつけています。
小牧山に1本しかないトチノキの花は豪華な感じ。
ふもと東のタニウツギも咲き始めています。
27日の観察、東遊歩道でサンショウクイと出会いました。
連日、気温が20度を超すようになったので木の洞から2匹のヤモリが出ていました。
【4月27日更新】
○青色、赤色の次は黄色
4月25日、オオルリやアカハラを観察した桜の馬場に黄色が目立つキビタキが登場しました。
最初は桜の枝葉で隠れるように。
次はカエデの葉の後ろ。
そして、全身を披露。
お腹を見せることも。
同じ仲間のコサメビタキも登場してくれました。
オオルリはオスだけでなくメスも姿を。
アオジやアカハラも姿を見せてくれました。
太くて大きなクチバシが目立つシメも登場。
【4月24日更新】
○渡りの途中のアカハラ
4月23日、前回オオルリを観察した桜の馬場にいると、ユリノキにアカハラが飛んできました(下の写真)。
山頂まで観察して桜の馬場に戻りしばらくすると、今度はカエデの木にアカハラが飛来。
お稲荷さんに移動しシジュウカラやヤマガラを観察していると、2羽のアカハラが飛んできました。
小牧山はオオルリやコマドリのような夏鳥やアカハラのような冬鳥が繁殖地まで移動する休憩地になっています。
渡りをしないヤマガラやシジュウカラは今子育ての真っ最中。雛のため餌となる青虫をくわえて運ぶようすを見ることができます。資料によると、1羽のシジュウカラが1年間で食べる青虫は125,000匹だそうです。
【4月23日更新】
○夏鳥が飛来しました
4月21日の朝、桜の馬場周辺でコマドリの美しい鳴き声が響いていました。
残念ながらコマドリは撮影できませんでしたが、声が聞こえた場所で青色が美しい数羽のオオルリが飛び回っていました。ただし、青いオオルリはオスでコマドリに負けないくらいの鳴き声でさえずります。
市役所近くにある忠魂碑にある大型の花をつけるツツジのオオムラサキの花数が増えてきました。
あちこちで小さい花のツツジも花の数を増やしています。
野草のハルジオンも咲き始めました。もう少しあとに咲くヒメジョオンとよく似ています。
若い茎を食用にする野草のイタドリも茎を伸ばしてきました。
【4月17日更新】
○詩(うた)に出てくる花
4月16日、2週間ほど楽しませてくれた桜に代わり、山のふもとに咲く黄金色の花の山吹。
兼明親王の和歌「七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき」が太田道灌の山吹伝説に出てきます。
最初の2枚は八重咲き、上の1枚は一重咲きの山吹で八重咲きの山吹には実ができません。
ふもとには別名「卯の花」と呼ばれるウツギ(空木)の白い花が咲き始めました。
童謡「夏は来ぬ」の歌詞の最初に「卯の花の匂う垣根に…」と出てきます。
市役所に近い道路沿いの花壇にはシラン(紫蘭)も咲き始めていました。
北のふもとではツツジの仲間も咲き始めています。
桜の馬場近くでは花の形が違っているドウダンツツジの白い花もありました。
【4月13日更新】
○桜花の名残を惜しむ
4月12日、花びらを落とし始めたソメイヨシノに若葉が出始めています。
大手道の標本木には名残を惜しむかのようにスズメが来ていました。
中腹の桜の馬場では桜花にメジロの群れが飛来していました。
五段坂を乗り切ったところに咲く八重桜。
山頂の草原に乱れ咲く野草のマツバウンラン。
常緑樹のクスノキの新しい赤みをおびた葉っぱが出てきました。新しい葉っぱが出てくると古い葉っぱは地面に散っていきます。
若い葉っぱを出したヤツデも見つけました。
【4月12日更新】
○桜花の締めは八重桜
4月10日、早咲きの河津桜からソメイヨシノと楽しんできた桜花の締めの八重桜が咲き始めました。
桜より一足早く咲き終わった梅には実ができはじめています。
小牧山に1本しかないトチノキには若葉やつぼみが出てきました。
散った桜の花びらにテングチョウ。
梅園のタンポポにも桜の花びらや散り始めたクスノキの葉っぱが。
お稲荷さんの日陰にいる冬鳥のシロハラの周りにも花びらや葉っぱ。
東のふもとでは地面でシメが餌をついばんでいました。
ふ化したばかりのナナフシの幼虫を見つけました。
コロナウイルスの関係で出かける場所がない親子連れの姿をあちこちで見ました。
【4月7日更新】
○ツツジが準備を始めました
4月7日、穏やかな天気な日。
小牧山の桜は満開を過ぎ散り始めています。
桜花を追いかけるように小牧市の花「ツツジ」の仲間が主役交代の準備を始めました。
桜を楽しみに来訪する人があちこちに。
この日のヒヨドリはカエデの花を食べていました。
冬鳥のツグミやアオジの姿を見ることができるのもあとわずか。
カタクリの近くにあるフッキソウに成虫で冬越しをしたルリタテハがひなたぼっこを。
【4月3日更新】
○好天のもと満開
4月3日、前日は強い風が吹き肌寒さを感じましたが、この日は朝から好天。
小牧山の桜は満開を迎え、お天気のよさも幸いし朝から多くの花見客が訪れていました。
しだれ桜や山桜も競い合うように咲いています。
ヒヨドリは前回のように桜花をちぎることなく、花の蜜を吸っていました。
山頂付近も見ごろ。
桜の花を追いかけるように、気の早いツツジの仲間が咲き始めました。
ハナカイドウも間もなく見ごろになりそう。
野草のムラサキケマンも咲いていました。
週末の土日は花見日和になりそうですね。
【3月31日更新】
○雨が降りそうな曇り空の桜花
3月30日、今にも雨が降りそうな天気でした。
途中から雨がポツリ・ポツリすることもありました。
小牧山の桜はちょうど見ごろ、青空がバックだともっと桜花がきれいに見えると思います。3月30日、今にも雨が降りそうな天気でした。
「れきしるこまき」の丘に種類が違う桜花も見ごろ。
食欲旺盛なヒヨドリは桜花やコブシの花を愛でることなく、花を無粋にむさぼり食べていました。
梅園の梅花に変わり、周囲の桜花が主役交代。
その桜花に50羽を超すと思われるメジロの群れが訪れていました。
閉館中の歴史館前の桜も見ごろ。
桜の馬場も見ごろでしたが、天気が悪いので来訪する人はまばら。
山桜には北のふもとと同じようにメジロの群れ。
明後日から天気がよくなるとの天気予報、週末にかけて見ごろの桜花を楽しむことができそうですね。
【3月27日更新】
○今日は朝から雨
3月27日、朝から雨の降る日。
雨の日は訪れる人もまばらでした。
南の入り口近くはいろいろな花が競い合って咲いていました。
ハナカイドウや花梨。
こんな桜の仲間も。
「れきしるこまき」前の桜。山頂の歴史館ともども4月いっぱい閉館になりました。
天気がよければにぎわう桜の馬場も静か。
目立たないカエデの花も咲き始めました。
雨が降っていても小牧山の春は進行しています。
【3月26日更新】
○今週末が見ごろでしょうか
大手道入り口にある標本木の花数が日ごとに増えています。
好天が続いているので、親子の姿があちこちに。
山頂歴史館と桜を西から見上げて撮ってみました。
先日までふもとの梅園を訪れていたメジロが山頂の桜に集まっていました。
「れきしるこまき」前の桜はまだこれからという感じ。
「れきしるこまき」近くのハナカイドウや花梨は開花間近。
コブシが見ごろになりました。
北のふもとの井戸にカワセミがいました。
食欲旺盛なヒヨドリがクロガネモチの実や桜の花を食べる姿を見ました。
今週末が桜の見ごろになりそうですが、無情の雨が降るとの天気予報が…。
【3月22日更新】
○ 標本木の開花宣言は明日?!
3月22日、小牧山の大手道入り口にある標本木を見ると数輪の花。大半はつぼみですが、この調子でいけば明日は開花宣言できるのではと思います。

道路沿いのしだれ桜は一足早く咲き始めました。
前回紹介した山頂歴史館前の桜は花数を増やしています。
山頂手前の桜は一気に花が咲いてきました。
梅園近くの桜で開花を待ちわびるモズがいました。
桜の馬場の桜も、まだまだこれからという感じでした。
「れきしるこまき」前のしだれ桜は濃いめのピンク。
北のふもとで薮の中を動きまわる数羽のウグイスを見ました。
朝から穏やかな天気の3連休最終日は子どもを連れた家族が多数来ていました。
次回は標本木の開花のようすが紹介できるのではと思っています。
【3月19日更新】
○山頂の桜が開花
3月19日、小牧山の山頂の桜が咲き始めました。
昨年秋に花を咲かせた四季桜がまた花数を増やしてきました。
北のふもとから見上げた中腹にピンクが目立つ桜も咲き始めています。
前回お知らせをした東遊歩道から見上げた桜は見ごろになっています。
市役所に近い道路沿いにあるしだれ桜のつぼみはご覧のようすでした。
北のふもとにあるカタクリが見ごろになっていました。
山際に立ち入らないようロープで区切ってあります。
大手道脇に野草のキランソウが咲いていました。
別名ジゴクノカマノフタ(地獄の釜の蓋)といい万病に効く薬草。
別名の由来はいろいろありますが、地獄の釜の蓋が開く春の彼岸のころに花が咲くからという説も。関心のある方は由来を調べてみてください。
暖かくなり成虫で越冬したムラサキシジミを見ました。
日当たりのよい場所でひなたぼっこをするように翅を広げていました。
前回の梅園で紹介したテングチョウもひなたぼっこをしていました。
小牧山は梅から桜の季節に移行しています。
【3月17日更新】
○ 間もなく開花
3月15日の朝、小牧山の山頂の桜はつぼみの先のピンクが目立つようになってきました。
山頂から御嶽山などの雪山がきれいに見えました。
北のふもとの東遊歩道への登り口から見上げると数多くの花をつけた桜が見えました。この木は毎年一番早く花をつけています。
ふもとのユキヤナギは日に日に花数を増やしています。
梅園の紅梅の蜜を求めてメジロが数羽来ていました。
れきしるこまき近くのハナカイドウもつぼみが出てきました。
タラノキの芽も出ていました。
例年より一段と早い小牧山の春がスタートしそうですね。
【3月14日更新】
○ 春の準備が進行中!
3月13日の朝、小牧山には多数のウオーキンググループが来ていました。
目立つハナモモやウメなどの花だけでなく、小さなカエデの芽吹きや花を見つけました。
桜の花芽も咲く準備をしています。
花梨やコブシはつぼみを出してきました。
山の中には枝にびっしりと花をつけたヒサカキの香りが漂っています。
市の木になっているタブノキの芽も目立つようになりました。
山頂のクロガネモチの実をヒヨドリが食べていました。
1月下旬から約1か月間、美濃加茂市の太田宿を訪れていたヒレンジャクと思われる群れの一部が先週は市民四季の森、この日は小牧山に来ていました。この鳥は冬鳥で数年おきにしか飛来しない珍しい鳥、運がよいと出会うかもしれません。間もなく渡っていくと思います。
写真にはありませんがウグイスの「ホーホケキョ」という鳴き声も聞きました。
小牧山の春を五感で味わいましょう。
【3月10日更新】
○ 春の陽気に誘われて

3月9日、朝から晴れ渡り気温が一気に上昇した小牧山ふもとの見ごろとなった梅園に数多くの家族連れが訪れていました。

別の梅の木でも写真を撮ったりして、くつろいだりする姿もありました。

花数が増してきたハナモモやクスノキの下でもシートを広げる親子がいました。
梅園の白梅で成虫で冬を越したテングチョウが蜜を吸っていました。
咲きそろってきた紅梅ではメジロが吸蜜する姿も見ました。
【3月6日更新】
小牧山の自然観察7
○ 見ごろの梅園にカメラマン


3月5日、小牧山ふもとの北にある梅園の紅梅が見ごろになりました。
朝早くから見ごろの紅梅や白梅に来たメジロを撮りに来る人の姿も。
合瀬川土手やふもと北にある紅梅は見ごろがもう少し先になりそう。

桜の馬場で薮の中をちょこまかと動くウグイスがいました。
2月末の小牧山でウグイスの「ホーホケキョ」という初鳴きを聞いた人もいます。
私は昨日、市内東部にある市民四季の森で聞きました。

お稲荷さんのところでメジロやシジュウカラ、コゲラの群れと出会いました。
このような種類の違う小鳥の群れを混群(こんぐん)といいます。

ふもと南の出入り口で咲き始めのシャガ1輪を見つけました�
 日本語
日本語 English
English 简体中文
简体中文
 한국어
한국어